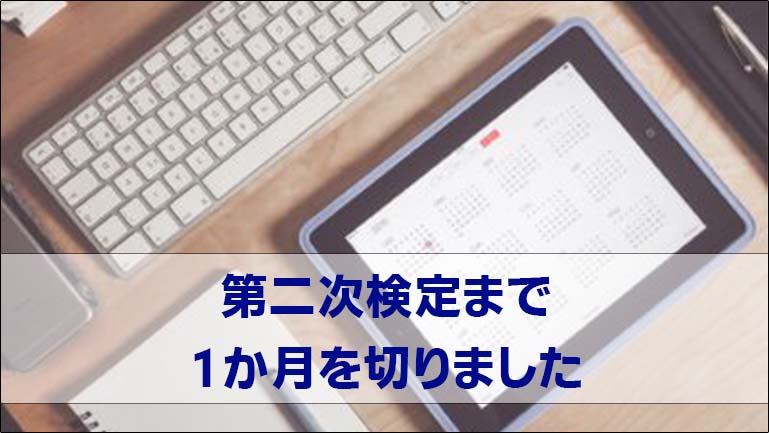
この記事を書いているのは9月20日火曜日です。令和4年の技術検定は、1級建築及び電気の場合は第二次検定として10月16日(日曜日)を予定しています。
試験まで3回の週末(3連休あり)と16日前日の15日土曜日が試験勉強として有効に使える時間です。
とは言っても、私の受検の際もそうでしたが全ての土日が有効に使えるわけではなく、仕事のある人も多いでしょう。
結論、毎日仕事をしようが、在宅勤務がメインであろうが、試験までの時間は皆同じ。
現在、少し勉強が遅れているなと感じている人は、改めてこの1ヶ月で勉強に使える時間を確認の上、取り組めることを真剣に考えるのも大事なワークです。私の受検時の事も思い出しながら、本記事をまとめたいと思います。
本記事を読むにあたり
基本的に真面目でコツコツタイプの受検生は、ある程度勉強が進んでいると思います。
まだ全く準備ができていない、極論するとどんな問題が出題されるかもまだ理解していない。
そんな人も過去の経験でも一定数います。(笑)
まだ情報収集段階である人は、
例年の出題の傾向とその対策を読んで欲しいと思います。
勉強時間をどれだけ確保出来るか?
1日どれくらい勉強すべきか?というのは以前のこの記事でもまとめています。
実地試験の2ヶ月少し前から勉強開始。平日毎日1時間。休日は2~3時間程度。
試験の1ヶ月前は、平日2時間。休日6時間。※当サイトより合格者へのアンケートより抜粋
そしてざっと平均すると、
平日は1時間〜1時間半、土日は4時間~6時間程度
※約25名のアンケート回答の平均値
当然かなり勉強時間を確保している方もいますよ。
これが平均値かと思います。
皆さんはどれくらい確保できそうでしょうか?
例えば9月20日(火曜日)〜10月15日(土曜日)まで実質26日です。
土日祝は9日× 6時間=54時間 計88時間
土日祝は9日× 5時間=45時間 計62時間
- 施工経験記述の記述練習
- 記述問題の対策(安全管理と仕上げ工事の可能性が高い)
- ネットワーク工程を理解するための学び
- 用語・数値の暗記(躯体工事と法規の可能性が高い)
やるべきことは多いですね。
勉強時間が仕事的にもあまり確保出来ない場合は、やはり重点分野、そうでない分野を検証して切り分けて考えましょう。
60点(6割)の正答率を目指すために
私の受検時も、試験終了後は何とかなるんじゃないかと思いつつも絶対的な自信はありませんでした。(合格発表まで4ヶ月は長かった)
それは全ての問題がバランスよく得点が取れたわけではなく、あまりうまく行かなかった問題も多かったからです。
・施工経験記述は書けそうだが、法規やネットワーク工程は嫌いだ。
- 経験記述・・・ほぼ完璧(多分)
- 仮設計画の留意事項・・せいぜい半分出来たかどうか?
- 躯体工事の留意事項・・上に同じ(笑)
- 仕上げ工事の正誤問題・・8問中 6問か7問の正解
- 工程(バーチャート)・・ほぼ正解だったと思う。
- 法規・・半分しか正解しなかった
②③⑥は半分しか正解していません。(2、3どちらかは半分切っているかも)
②と③の対策も最後の2週間頑張ったんですけどね、自分の出て欲しい問題は出ませんでした(笑)
(施工経験記述を頑張る戦略)
基本的に頑張れるならば満遍なく勉強すべきだけど、やはり多くの人の時間は限られていると思います。
試験対策が全般的に遅れて焦ってきた人は
- 一通りの施工管理法などの知識が頭に入っている。
- 施工経験記述の対策も目処がたった。
- あとは過去問の反復と記述練習をメインに
という人は、3つ目をひたすらやって、直前に施工経験記述のチェックをしろで良いと思うんです。
ちなみに私の場合、約1ヶ月前は、概ね施工経験記述は完璧ではないが、何とかなりそうだという実感を得ていた時期でした。
でも仕事もそこそこ忙しかったので、記述練習は十分とは言えませんでした。
記述問題があまりできなかった私がアドバイスするのも何ですが、記述の反復練習は2週間〜3週間あれば何とかなると思います。
私は過去10年の過去問を出題傾向と対策に留意して、上記期間でやり切った記憶があります。
なので、勉強が遅延気味な人はこのようにやってみる。
- これからの最初の1週間で施工経験記述の取り組み(ネタ決め)
- 残り2~3週間で過去問の取り組み
基本的に第二次検定受検者は、第一次検定の合格者です。なので施工管理法の一通りの知識があると思います。
ただし学科試験に合格して少し時間が空いた、という人は今から移動時間を活用して、最低限の知識を増やしていくことをお勧めします。
(というか、基本的には上記に限らず移動時間の活用は大きくプラスになります)
そしてですね、第二次検定試験、何とかなるんじゃないか?と自信がついてくるのは、施工経験記述がある程度書けそうだ、と思った時だと思います。
私は1年目仕事が超多忙で途中で勉強を挫折したのですが、その時は施工経験記述が書ける感じが全くなく、合格する自信もゼロでした。
書けるようになると、他の勉強も頑張って今年何とか受かろうと最後のパワーが出たのを強く記憶しています。
ここで宣伝ですが(笑)
昨年より施工経験記述添削指導サービスをやっています。
- 工事の状況における説明不足について、記述を加えることで改善される。(枕詞を加えるとよくなる)
- 表現方法を少し変えることで、施工管理者らしい表現に変わり改善される。
- 具体的な経験例をうまく記述できていないところをフォローアップ。
⇒これは第三者の指摘がないとなかなか気づきません。
⇒時間のない方はこれで過去の対策として重点取り組みが可能です。
勉強を習慣化するために
私は色んなことを始める場合、道具の購入からスタートするタイプです。
・添削指導をするときは、書きやすい赤ペンを探しまくった
・サイト運営用にはmacbook airを購入
・奥さんに何かねだる(笑)
8月からマイペースで勉強している人もいるし、
これからエンジンをかける人もいる。
長年見てきましたが、最後に頑張れば何とかなります。
引き続き、本試験まで記事を更新しながら、応援していきますので、残りの1ヶ月を効果的に勉強して欲しいと思います。


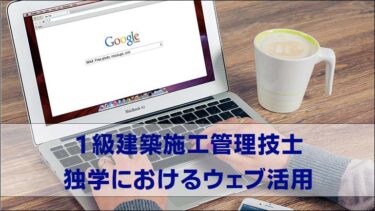


-1-375x211.jpg)
-375x211.jpg)
