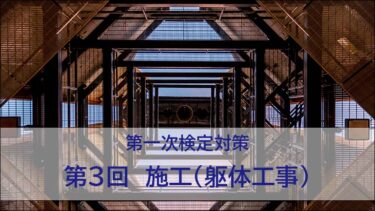第一次検定の過去問の取組み、今回は第5回の施工管理法関連の問題です。
これは令和2年まで午前、午後の試験で25問出題されていたので、2回に分けます。(令和3年は15問)
- 第5回・・・工程・計画や調査など
- 第6回・・・品質管理・安全管理など
またネットワーク工程関連の問題は、第二次検定を踏まえて基本的な知識を得ておくことは大切です。
施工管理法に関する出題分野の分析
まずは、過去3年でどんな問題が出題されているか分析してみましょう。
まずは午前の部の5問より。
| 番号 | 令和4年 | 令和3年 | 番号 | 令和2年 | 令和元年 |
| 40 | 仮設計画 | 事前調査・準備作業 | 46 | 仮設計画 | 事前調査 |
| 41 | 仮設計画(設備) | 仮設計画(設備) | 47 | 仮設計画(設備) | 仮設計画(設備) |
| 42 | 施工計画 | 材料の取扱い | 48 | 施工計画 | 施工計画(解体工事) |
| 43 | 建設工事の記録 | 労働基準監督署長への届出(安衛法) | 49 | 施工計画(躯体) | 施工計画(耐震改修) |
| 44 | 工期と費用 | 工程計画 | 50 | 施工計画(仕上) | 施工計画(仕上改修) |
次に午後の部の試験問題です。
| 番号 | 令和4年 | 令和3年 | 番号 | 令和2年 | 令和元年 |
| 45 | 工程計画及び工程表 | 工程計画(鉄骨工事) | 51 | 材料の保管 | 材料の保管 |
| 46 | タクト手法 | ネットワーク工程(フロート) | 52 | 建設工事の記録 | 労働基準監督署長への届出(安衛法) |
| 47 | 品質管理 | 品質管理 | 53 | 工程管理 | 工期と費用 |
| 48 | 試験と検査(鉄筋コンクリート工事) | 品質管理(図表) | 54 | 工程計画 | 工程計画 |
| 49 | 振動・騒音対策(鉄筋コンクリート造の解体工事) | 品質管理の検査 | 55 | タクト手法 | 工程計画(鉄骨工事) |
| 50 | 労働災害 | 公衆災害防止対策 | 56 | ネットワーク工程 | ネットワーク工程(用語) |
| 51 | 公衆災害防止対策 | 作業主任者の選任(安衛法) | 57 | 品質管理 | QC工程表 |
| 52 | 作業主任者の職務(安衛法) | 足場 | 58 | 品質管理の用語 | 品質管理の用語 |
| 53 | 事業者の講ずべき措置(安衛則) | 特定元方事業者の措置(安衛則) | 59 | 管理値 | コンクリートの管理値 |
| 54 | 酸素欠乏危険作業 | クレーン | 60 | 品質管理の検査 | 品質管理(図表) |
| 61 | 試験・検査(コンクリート) | 品質管理の検査 | |||
| 62 | 試験(タイル工事) | 外観検査(ガス圧接) | |||
| 63 | 振動・騒音対策(鉄筋コンクリート造の解体工事) | 試験・検査(仕上げ工事) | |||
| 64 | 労働災害 | 労働災害 | |||
| 65 | 公衆災害防止対策 | 公衆災害防止対策 | |||
| 66 | 作業主任者の職務(安衛法) | 作業主任者の選任(安衛法) | |||
| 67 | 足場 | 足場 | |||
| 68 | 事業者が行うべき点検(安衛則) | 事業者の講ずべき措置(安衛則) | |||
| 69 | ゴンドラ作業 | クレーン | |||
| 70 | 酸素欠乏危険作業 | 有機溶剤業務 |
令和3年より問題数としては10問減りましたね。なので少し傾向は読みにくいので、一通りの履修は必要ですね。
今回は、仮設計画と工程計画の問題を取り上げたいと思います。
1.施工管理法~仮設計画(設備)に関する出題
1つ目は仮設計画(設備)に関する出題です。これは毎年出題されています。
【問題】仮設設備の計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 必要な工事用使用電力が60kWのため、低圧受電で契約する計画とした。
- 工事用使用電力量の算出において、コンセントから使用する電動工具の同時使用係数は1.0として計画した。
- 作業員の洗面所の数は、作業員45名当たり3連槽式洗面台1台として計画した。
- 仮設の給水設備において、工事事務所の使用水量は、1人1人当たり50Lを見込む計画とした。
- 解答・解説
- (解答)①
(解説)多くの問題が過去問で頻出されています。
①(令和元年)工事用使用電力が60kWが必要になったため、低圧受電で契約する計画とした。
⇒高圧受電設備は受電容量が50kW以上2,000kW以下と定められているので、低圧受電は誤りなので、①が正解です。
※50kW未満は低圧受電、2,000kW以上は特別高圧受電となっています。
②(令和元年他)工事用使用電力量の算出に用いる、コンセントから使用する電動工具の同時使用係数は、1.0として計画した。
③これは初めての出題ですね。私も知らなかったのですが、JASS2仮設工事で定められているようです。
④(平成30年他)仮設の給水設備において、工事事務所の使用水量は、50L/人・日を見込む計画とした。
基本的には毎年出題されている仮設設備の問題は、過去問で数値をしっかり記憶しておきましょう。
2.施工管理法~施工計画に関する出題
次に施工計画の問題です。この施工計画は躯体や仕上げ、解体、改修など幅広く出題されるのが特徴。
一昨年の令和2年の問題を取り上げます。
【問題】施工計画に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
- 鉄骨工事において,建方精度を確保するため,建方の進行とともに,小区画に区切って建入れ直しを行う計画とした。
- 大規模,大深度の工事において,工期短縮のため,地下躯体工事と並行して上部躯体を施工する逆打ち工法とする計画とした。
- 鉄筋工事において,工期短縮のため,柱や梁の鉄筋を先組み工法とし,継手は機械式継手とする計画とした。
- 鉄骨工事において,施工中の粉塵の飛散をなくし,被覆厚さの管理を容易にするため,耐火被覆はロックウール吹付け工法とする計画とした。
- 解答・解説
- (解答)④
(解説)いつもの通り、過去の出題から正誤を導いていきます。
①(平成27年)鉄骨工事において、部材の剛性が小さい鉄骨のため、大ブロックにまとめて建入れ直しを行う計画とした。
⇒平成27年の問題は全く逆の記述ですが、極力小区画に区切って建入れ直しを行うことが良いとされています。
②(平成28年他)大規模,大深度の工事のため、地下躯体工事と並行して上部躯体を施工することにより、全体工期の短縮が見込める逆打ち工法とする計画とした。
③(平成28年)鉄筋工事において、工期短縮のため柱と梁の鉄筋を地組みとするので、継手は機械式継手とする計画とした。
④(平成29年)鉄骨工事の耐火被覆は、施工中の粉塵の飛散がなく、被覆厚さの管理の容易なロックウール吹付け工法で実施する計画とした。
⇒ロックウールの吹付けは施工中の粉塵飛散は多いですね。この④が正解となります。
3.施工管理法~工程計画に関する出題
次は工程や工期に関する問題ですが、これも毎年出題されています。
最新の令和3年の問題を取り上げます。
【問題】工程計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- マイルストーンは、工事の進捗を表す主要な日程上の区切りを示す指標で、掘削完了日、鉄骨建方開始日、外部足場解体日等が用いられる。
- 工程短縮を図るために行う工区の分割は、各工区の作業数量がほぼ均等になるように計画する。
- 全体工期に制約がある場合、積上方式(順行型)を用いて工程表を作成する。
- 工程計画では、各作業の手順計画を立て、次に日程計画を決定する。
- 解答・解説
- (解答)③
(解説)今回の選択肢はすべて過去に出されているものです。今回は、過去問からではなく、きっちり解説します。
①マイルストーンは工程を守る上で、その進捗を理解する上でのポイント(指標)となるもので、鉄骨建方、足場解体などはまさに工程を順守して行く上でのマイルストーン(道標)になりますね。
②工区を分割する際、作業数量がバランス悪いと、工区毎に進捗にバラつきが生じます。作業数量は均等になるようにすべきですね。
③積上方式(順行型)は言葉の通り、工事着工から順に各工事を策定していく方式なので、工事完了は積み上げた結果の日程となります。
工期の制約がある場合は、割付方式(逆行型)として、決まった工期から逆算して工程を割り付けていく方式で作成すべきですね。
よってこの③が正解となります。
④工程計画では、書いてある通り、まず作業の手順計画を立てたうえで、各工事に対して日程を算出していきます。
この問題は、用語と内容を丁寧に読み込んで解答しましょう。
4.施工管理法~ネットワーク工程に関する出題
今回の最後はネットワーク工程の問題です。例年、出題されるのは1問です。(令和4年は出題なし)
なのであまり意識する必要もないのですが、第二次検定は大問として1問ネットワーク工程の問題がここ6年程出題されています。
基本的な概念と用語の意味を理解出来ると、2次検定対策の際少し楽になりますよ。
逆に言うと、この基本知識がないと2次検定で少し苦労することになります。
こちらは令和2年の問題を取り上げます。
【問題】ネットワーク工程表に関する記述として,最も不適当なものはどれか。
- ディペンデントフロートは,後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロートである。
- フリーフロートは,その作業の中で使い切ってしまうと後続作業のフリーフロートに影響を及ぼすようなフロートである。
- クリティカルパスは,トータルフロートが 0 の作業を開始結合点から終了結合点までつないだものである。
- トータルフロートは,当該作業の最遅終了時刻 (LFT) から当該作業の最早終了時刻 (EFT) を差し引いて求められる。
- 解答・解説
- (解答)②
(解説)こちらはそれぞれの用語を解説していきます。
・トータルフロート・・・ある作業を最早開始時刻でスタートして、後続作業を最遅開始時刻で始める場合でその作業がもつ余裕日数。
最遅終了時刻(LFT)ー最早終了時刻(EFT)がトータルフロートになります。
・ディペンデントフロート・・・後続作業に影響するトータルフロートのことで、トータルフロートからフリーフロートを引いて求めることで出来ます。
・フリーフロート・・・ある作業を最早開始時刻でスタートして、その次の後続する作業が最早開始時刻で始めたとしても余る余裕日数。
(後続作業に影響しない)
・クリティカルパス・・・工程の最長経路の事。ネットワーク工程の各つながった工程を結んだ時の一番長い経路のこと。
※工期短縮を検討する際は、このクリティカルパスのどこかを短縮する必要があります。
よって解答は②ですね。
ネットワーク工程に関しては下記記事も参照ください。
まとめ
一昨年(学科試験時代)までは、この施工管理法の問題が、一番合否に影響を与えるというまとめにしていましたが、
- 施工管理法 25問⇒15問
- 施工(躯体工事) 5問⇒7問
- 施工(仕上げ工事)5問⇒7問
- 施工管理法の応用問題 6問(5~6問が躯体工事及び仕上げ工事から出題されている)
よりバランスの良い学習が必要となっています。
次回の第6回も施工管理法(後半)に続きますが、品質管理や安全管理に関する問題に取り組んでいきたいと思います。
第6回の記事はこちら。
過去問の取り組み(第1回〜第4回)
1級建築施工管理技士の第一次検定対策の過去問の取組みは前回は建築学を取り上げました。 1級建築施工管理技士 第一次検定(学科試験 )過去問の取組み〜第1回 建築学 今回は、例年の問題16~20で出題される『設備・契約(施工全般)[…]
第3回の施工(躯体工事)に続いて、今回は施工(仕上げ工事)の問題を取り上げたいと思います。 昨年より重要性がより増した施工関連の問題、ここで大きく点を失う事のないようにしたいところです。 どんな問題が出題されているのか理[…]
さて前回の過去問の取組み、第2回 共通(設備・契約)に続き、第3回の施工(躯体工事)に取り組んでみましょう。 令和3年度の第一次検定より、より重要性が増したのは施工(躯体及び仕上げ工事)[…]
さて令和6年(2024年)の第一次検定対策、出題分野別にどんな問題が出題されているのか? どう取り組んでいくべきか、例題に触れながら取り組んでいきたいと思います。 まずは例年に、問題1~15に出題されている建築学について[…]