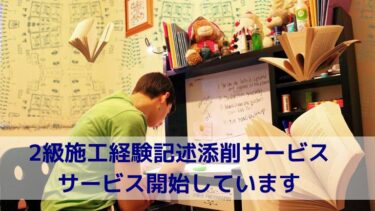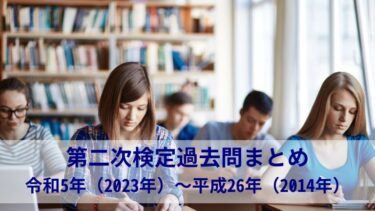昨年に引き続き、令和5年度(2023年)の2級建築施工管理技士の第二次検定について、問題構成と出題傾向及びその対策についてまとめていきたいと思います。
令和6年度版を新たにアップしました。
一昨年の令和3年より実地試験→第二次検定と試験制度も変わり、少しですが出題方式も変わりました。
今年は新たな試験制度で3年目ですが、基本的に勉強の進め方は従来と変わりません。ただ、施工経験記述は少し難しくなっている感じですね。
そのあたりも踏まえて良く準備をしていきたいものです。
・今年の施工経験記述はどうなる?
・例年の出題傾向は
・各問題毎の傾向と対策
2級建築施工管理技士の試験基準(第二次検定)
一昨年度の試験制度の改正により、2021年の第二次検定からは下記の通りとなっています。
| 検定科目 | 知識能力 | 検定基準 | 解答形式 |
| 施工管理法 | 知識 | 1 主任技術者として、建築一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。 | 四肢一択 |
| 能力 | 2 主任技術者として、建築材料の強度等を正確に把握し、及び工事の目的物に所要の強度、外観等を得るために必要な措置を適切に行うことができる応用能力を有すること。 | 記述 | |
| 3 主任技術者として、設計図書に基づいて、工事現場における施工計画を適切に作成し、及び施工図を適正に作成することができる応用能力を有すること。 |
主任技術者としてふさわしい施工管理能力(施工計画・品質管理・工程管理)とそれに対応するために必要な知識をしっかり持っているを求められています。
第二次検定の出題構成
令和2年(2020年まで)の出題構成は下記の通りでした。(いわゆる実地試験)
- 施工経験記述
- 施工管理の用語とその留意事項
- 施工管理(工程)
- 法規
- 施工の正誤問題(建築・躯体・仕上げに分かれる)
以上の5問で構成されていました。
令和3年の第二次検定より、『施工管理法における四肢一択の問題が出題される』と発表されましたが、それは下記の通りの構成となりました。
- 施工経験記述
- 施工管理の用語とその留意事項
- 施工管理(工程)
- 法規(四肢一択方式に変更)
- 施工の穴埋め問題(四肢一択に変更)
従来の問題4法規と問題5施工の問題が記述式から四肢一択に変更になったのみにとどまりました。
ですので、第二次検定という試験制度になった今後も実地試験を含めた過去問を中心とした取り組みでの試験準備で問題ないと言えます。
独学での勉強を進める方は、まずは自分に合ったテキスト選びが必要ですね。
またこの第二次検定は60%以上の得点で合格と言われていますが、その配点について下記の記事で取り上げています。(当サイトにおける配点予想)
第二次検定の傾向とその対策
問題1 施工経験記述
2級建築施工管理技士も1級建築施工と同様に、最初の問題1の施工経験記述が合格不合格を左右する最も重要な問題と言って良いでしょう。
出題に対し極力忠実な内容で解答できるようにする訓練が必要となってきます。
ここ最近の傾向として出題されているテーマは3つです。
- 品質管理(令和4年)
- 施工計画(令和3年)
- 工程管理(令和2年)
- 施工計画(令和元年)
- 品質管理(平成30年)
私の知る限り、以前までは2級は基本的に施工経験記述は出題ローテーションはほぼ順序通りでしたが、令和3年は順番的に言うと『品質管理』の出題だったのですが、『施工計画』が出題されました。そして昨年は品質管理が出題されました。
今年は『施工計画』と『工程管理』を主として準備しておく必要がありますね。
記述すべき内容は、
問題1-1は『あなたが経験した建築工事』について、
- 工事概要(工事名・時期・規模・実施した工事内容・あなたの立場)
- 工種名(鉄骨工事、防水工事など具体的な工種)
- 実施した内容や検討・留意した事項、また理由などを記述する。
という内容です。
例えば令和4年の問題を例を取ると、(品質管理)
1, 工事概要であげた工事であなたが担当した工種において, 施工の品質低下を防止するために取り組んだ事例を 3 つ選び, 次の①から③について具体的に記述しない。
ただし, ①は同一でもよいが, あなたの受検種別に係る内容とし, ②及び③ はそれぞれ異なる内容とする。また, ③の 行 ったことは「設計図書どおりに施工した。」等行ったことが具体的に記述されていないものや品質管理以外について記述したものは不可とする。
① 工種名又は作業名等
② 品質低下につながる不具合とそう考えた理由
③ ②の不具合を発生させないために 行ったこととその際特に留意したこと
- 何らかの管理項目を守らないと、品質上の不具合の恐れがある。(塗装のウキや床レベルの不陸など)
- そうならないように、どのような点に留意をして施工を行ったか。
良い品質を提供するために、実際に行った事を書ければ良いでしょう。
2, 工事概要であげた工事及び受検種別にかかわらず, あなたの今日までの建築工事の経験を踏まえて, 施工の品質を確保するために確認すべきこととして, 次の①から③をそれぞれ 2つ具体的に記 述 しなさい。ただし, ①は同一でもよいが, ②及び③はそれぞれ異なる内容とする。また, ②及び③は「設計図書どおりであることを確認した。」等確認した内容が具体的に記 述 されていないものや 1. の②及び③と同じ内容を記 述 したものは不可とする。
- 工種名又は作業名等
- ①の着手時の確認事項とその理由
- ①の施工中又は完了時の確認事項とその理由
- 塗膜防水工事
- 塗膜防水を塗る前に、下地の乾燥度を確認。⇒膨れが発生する恐れがあるため。
- 塗膜防水施工後、膜厚を確認した。⇒一定の膜厚が確保出来ないと、求められる防水性能が確保できない。
と言った感じでしょうか。2級の問題1-2としては少し難しかったように思います。
施工経験記述の問題1-2の対策はこちら
また本記事は1級向けに書いたものですが、施工経験記述を新築工事ではなく改修工事や大規模修繕工事で書こうと思っている方も多いと思います。そんな方向けに書いた記事がこちらです。
昨年度より施工経験記述の添削サービスを開始しています。(本年度は10月末日まで申込受付中です)
確実にミスなく高得点を取る支援サポートを手厚く行っています。こちらのページにサービス内容をまとめています。
今年は新たな試験制度ということで、問題内容も変わることからこの施工経験記述はしっかり取り組んでおきたいところです。
問題2 施工管理(用語)
問題2は建築用語が合計14個提示されて、そのうち5個を選んで、その用語の説明と施工上の留意事項を記述する問題です。
例えば、昨年の令和4年に出題された用語を見てみましょう
| 用語の記号 | 用 語 |
| a | 足場の壁つなぎ |
| b | 帯筋 |
| c | 親杭横矢板壁 |
| d | 型枠のセパレーター |
| e | 壁のモザイクタイル張り |
| f | 先送りモルタル |
| g | セッティングブロック |
| h | タイトフレーム |
| i | 天 井 インサート |
| j | ベンチマーク |
| k | 防水工事の脱気装置 |
| ℓ | マスキングテープ |
| m | 木構造のアンカーボルト |
| n | 溶接のアンダーカット |
問題3 施工管理(工程)
問題3はここ5年はバーチャート工程の問題が出題されています。
その前までは、ネットワーク工程に関する出題だったので、まさに1級と2級が入れ替わった感じです。
※同じ時期に1級はバーチャート工程からネットワーク工程の問題に変わった。
バーチャート工程の問題は、
- 工程表のあるチャートが何の工事(工事名)かを解答する。
- ある工事の完了日(終了日)を解答する。(月の上旬・中旬・下旬)
- ある時期までの累積出来高の金額やパーセントなどを解答する。
令和4年度の問題は、
- 作業名を2つ解答
- 出来高表から1月迄の累計金額と比率を解答
- 工程表から完了時期が不適当な作業を解答し、適切な完了時期を解答する。
- ③に合わせて適切な実績累計金額(出来高)を解答
出来高は単純な計算問題なので、過去問を演習すれば問題ないと思います。
工事はここ5年は鉄骨造、2017年は木造在来軸組工法でしたが、バーチャート工程で全体の工程の流れを理解して慣れる必要があります。
問題4 法規 ※四肢一択
法規は3問構成で、令和4年度の問題は、
- 建設業法
- 建築基準法(※10年のうち6年は建築基準法施行令)
- 労働安全衛生法(※10年のうち2年は建設リサイクル法)
1級建築施工管理技士の第二次検定は、建設業法・建築基準法施行令・労働安全衛生法の3つのみがこの10年出題されていますが、2級は建築基準法と建設リサイクル法も出題されています。各法令はとても多くの条文がありますが、出題される範囲はある程度定まっています。
令和2年(実地試験)までの出題方式は条文があって、3つの下線部の語句から誤ったものを一つ選択し正しい語句を記入する問題です。
⇒昨年度より下記の通り変わりました。
・空欄に当てはまる正しい語句・数値を4つの選択肢より選ぶ問題に変わった。(1問につき2つの空欄×3問)
いずれにしてもある程度出題される法規や条文の出題傾向に変わりはないので、過去問題の出題された条文をしっかり読み込んで記憶する必要があります。
この10年間で出題された法規及びその条文が何条なのかをまとめたのが下記の記事です。ある程度の出題傾向が把握できるのでしっかり準備して取り組んで欲しいですね。(但し、過去に出題されていない問題が出る可能性も十分にあります)
問題5 施工管理の穴埋め問題(建築・躯体・仕上げ) ※四肢一択
最後の問題5は受検種別毎の出題となっており、建築・躯体・仕上げの受検種別ごとに出題問題は異なります。
これは2018年度(平成30年度)以降はそのような形となっています。
まずは令和2年までの出題方式は8問あり、それぞれの問題の文章が、
・間違っている場合は正しい語句・数値を記述
する問題です。
令和3年の第二次検定より出題方式は変わりました。
・問題は8問
※建築は8問、躯体及び仕上げは4問×2で計8問解答(要するに同じ)
・各工事の記述において、空欄に当てはまる適当な語句及び数値を4つの選択肢より選ぶ。
⇒法規と同じ形式
こちらも平成30年度以降の出題分野を別途、夏頃までにまとめたいと思いますが、問題は以外と分散しています。
ここの知識は1次検定での内容が大切なように思います。
まとめ
この2級建築施工管理技士の技術検定ですが、基本的には1級と出題範囲が大きく変わることはないので、きっちり勉強をする必要があります。まあ基本的には過去問です。そして施工経験記述は自分オリジナルの記述が出来るようになることが重要ですね。
- 施工経験記述は徹底した記述の練習(3つのテーマ) ※少なくとも昨年度以外のテーマには取り組みましょう。
- 施工の用語は過去の出題を見ながら、ある程度得意分野に注力する。
- 施工管理(工程)は5年分の過去問を取り組むのみで良いと思う。
- 法規は7年~10年分の過去問の取組みで問題ない。
- 施工の問題は過去問の反復+第一次検定の勉強と並行して知識の吸収。
要するに過去問ですね(笑)
この記事は試験まで内容を順次アップデートしていきますので、より出題傾向に注力出来るようサポート出来ればと思います。
1級を含めて、2級の記事更新情報はtwitterで更新しています。フォローしてもらえるとうれしいです。